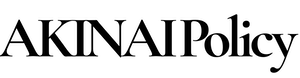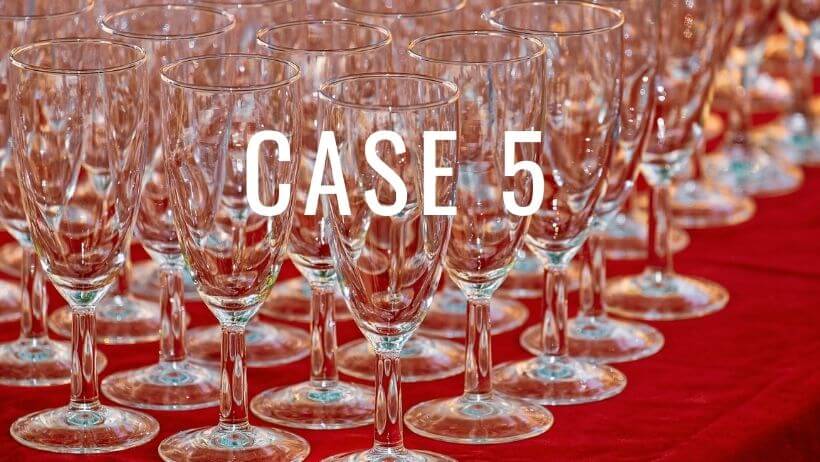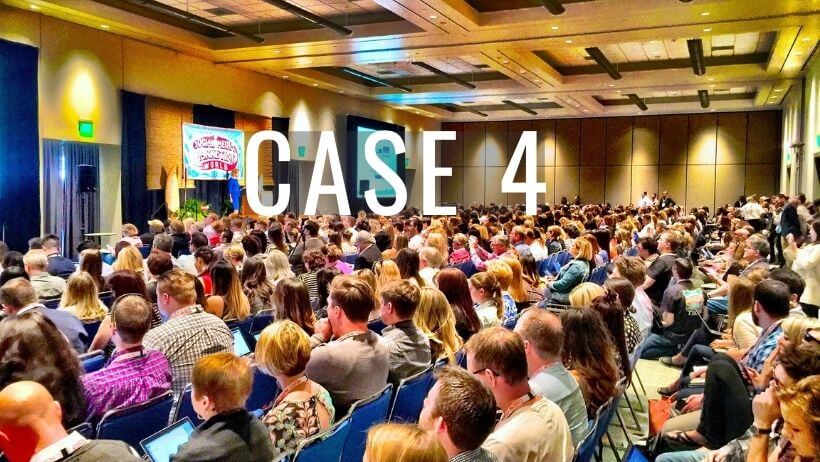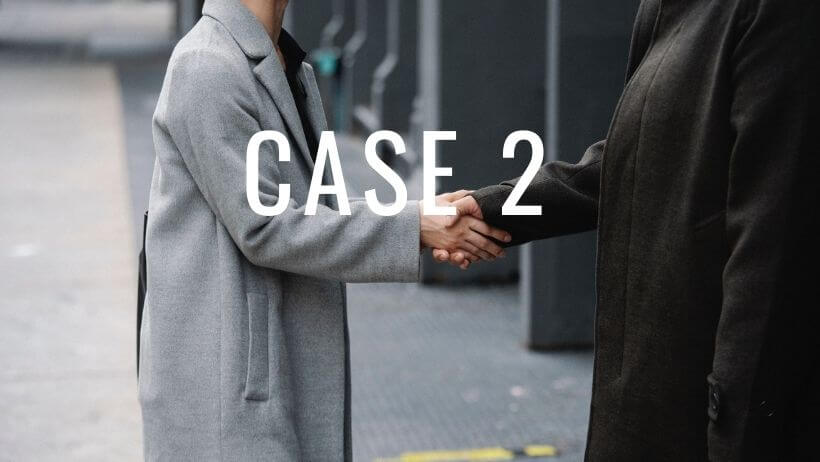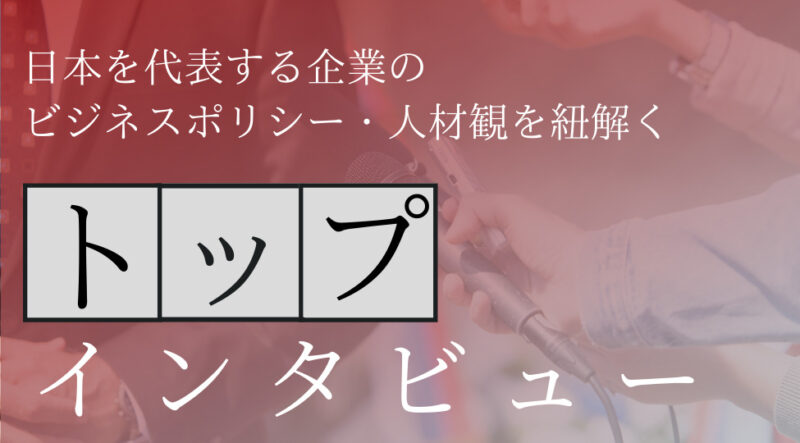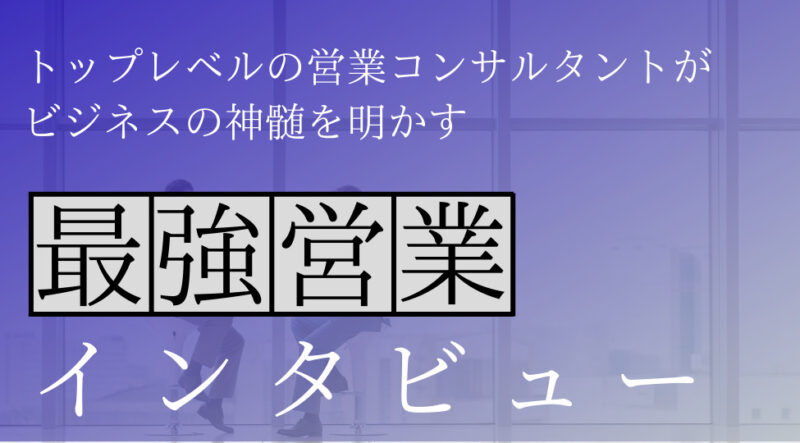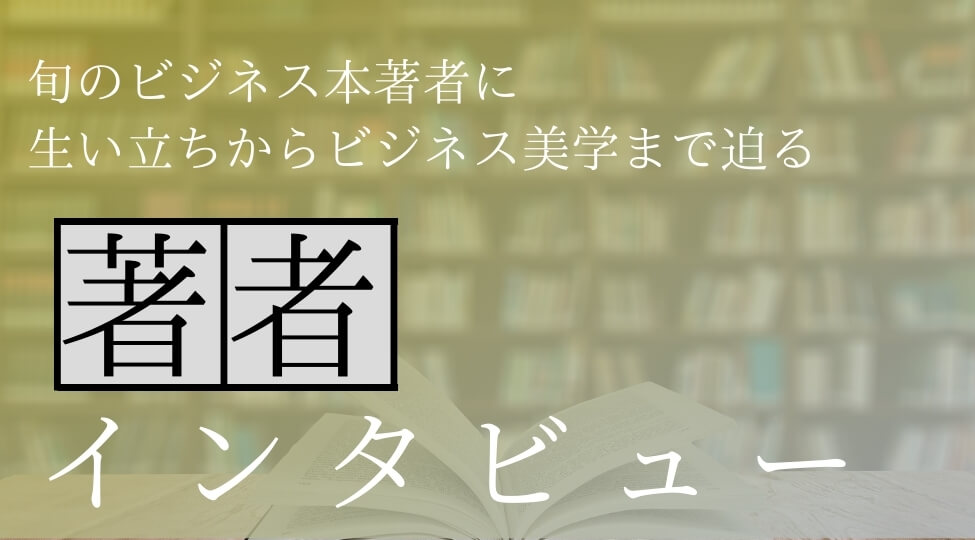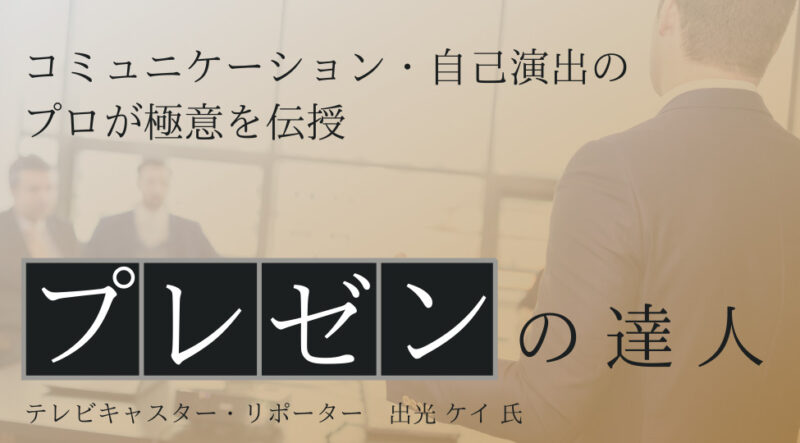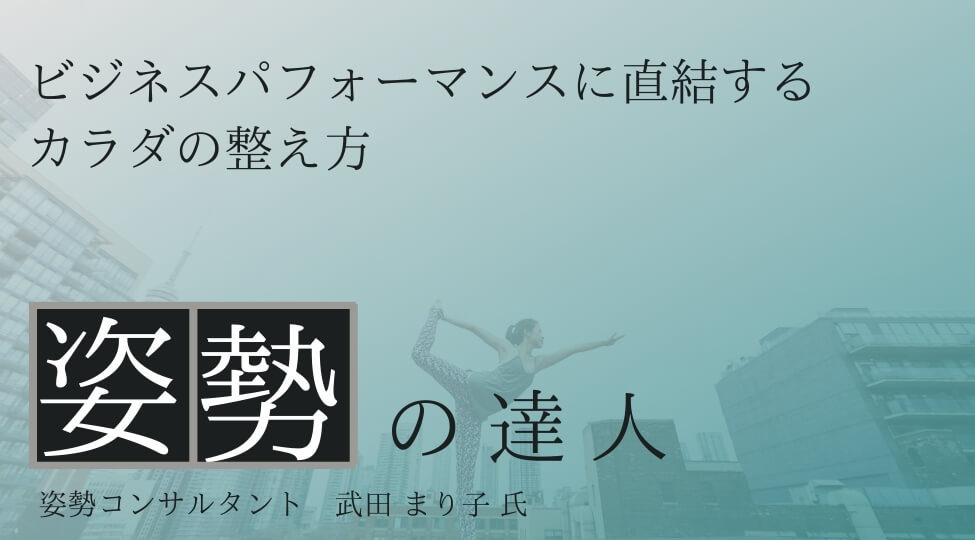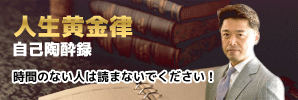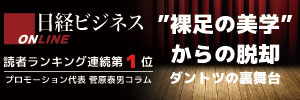プレゼンの達人Case3
会食や飲み会の席で
急に〆の挨拶を振られてしまったとき

昼間の堅苦しいビジネスの場以外-夜、食事やお酒の入る席-でのお客様とのコミュニケーションは重要です。
美味しい食事やお酒が入れば、人間だれでもリラックスし、普段とは違う一面が見えてきたり、お互い心を開いてコミュニケーションできる雰囲気になり、お客様との距離感をぐっと縮めることができるからです。
お客様との会話も弾み、「よしよし、これで明日からビジネスの話も進みそうだ!」と心密かに喜んでいるときに、「じゃあ、〆の挨拶は、今日の立役者**さんにしてもらおう!」なんて、急にあなたが指名された経験はありませんか?
宴もたけなわ、場も盛り上がり、お客様との信頼関係を深めて、いい雰囲気になったところで、あなたに任された役割は重大です。 画竜点睛を欠くという言葉もあるとおり、ここで失敗したら、これまでの時間が台無しです。
こんなときに、文字通りビシッと締まる挨拶の秘訣をご紹介します。
事前に準備しておけること
会食や飲み会でも、比較的改まった席であれば、事前に最初の挨拶、中締めを誰がするか、二次会はどうするかなど、段取りをしっかりとしていると思います。
ただし、そこまで改まった席でなければ、その時の空気の流れによって決めようという、これはこれであえてファジーにしておく場合もあるかと思います。
そんな時は、自分が〆の挨拶担当として事前に指名されていなくても、次のポイントは整理・準備しておきましょう。

- 今日の席の目的(意味)を理解しておく
今日の会食や飲み会がなぜ、どのような位置づけで設定されたものか。自分がなぜ、この席に並んでいるのか。これが、シメの挨拶で効いてくるキーワードになります。
単に、お客様との親交を深めるためとか、経費で美味しい食事とお酒にありつけるとか(まさかこのサイトを見ている人にそんな人はいないとは思いますが・・・)、漫然と参加しているようではビジネスパーソン失格です。
昼間の会議と同様、ビジネスの延長ですから、しっかりと目的意識を理解しておくことは基本中の基本です。 - 会の最中の出来事や会話に注意を払う
会の途中で全体で盛り上がった話題や会話、先に挨拶をした人の話の内容に注意を払っておきます。
ただ、飲んで騒いで、自分の僅かな周囲だけに気を配るのではなく、会全体に最初からよく注意を払い、シメの挨拶の時には、会の途中で出た話や前に挨拶した人の言葉を振り返って入れ込むと、より余韻が深まり、気の利いた挨拶になります。 - 飲み過ぎ注意、お料理は味わって
〆の挨拶を振られた時点には、1次会から飲みすぎて呂律が回らなかったり、おかしなテンションになっている、なんていうことは言語道断です。
楽しく飲んで、場を盛り上げることは大事ですが、あくまでもビジネスの延長ですから、飲みすぎには注意します。
また、お酌ばかりや話に夢中になってお料理に全く手をつけないのもいただけません。お料理は少しでも頂いておき、〆の挨拶のときに味の感想なども入れると、堅いだけではなく粋な挨拶になります。
その場でとっさに対応するコツ
〆の言葉には、いろいろなメッセージを持たせることができます。
上記の事前に準備できることも含めて、次のようなメッセージを伝えるためには、日ごろからの心持ちも大事です。日ごろ思っていること、感じていることを、アドリブで織り交ぜて述べればよいのです。
- 今日これまでと、この席に対する感謝
- 会社やプロジェクト全体だけではなく、席を同じくした今日のメンバー個々に対する敬意と今後へのさらなる期待
- 義理や義務ではなく、この席が設けられた意味を理解して前向きに参加する気持ち
表情など、言葉以外で気をつけること
ビジネスの一環とはいえ、お酒や食事が入れば、みんなリラックスしています。周りみんな飲んでいるのですから、変に堅い挨拶になるのは逆に興醒めです。
リラックスした雰囲気に相応しく、あなた自身もリラックスすれば、柔らかく粋で、且つその場全員の士気が一体化するような明るく前向き表情や声のトーンになるはずです。
〆といえば「一本締め」(または「三本締め」)と決めて疑わない人がいます。
その場の流れがありますから、無理に「お手を拝借ぅ~」とする必要はありません。その場の空気を読んで、臨機応変に対応しましょう。
ワンポイントアドバイス
ここまで、「責任重大」といった書き方をしてきましたが、お客様との親交を深めることが第一ですから、あまりかしこまって堅くなる必要はありません。
楽しい雰囲気、盛り上がった空気から自然な流れで、いったんその場に区切りをつけ、次(二次会でも明日以降の仕事でも)へスムーズな展開を促すためのスイッチングポイントであることを理解しておけば大丈夫です。
- 挨拶、スピーチの類は短く、スマートに。
- 次の展開や将来への期待感(コメント)は必ず入れる。
- 無理して〆ない。
(歓談中や既にお開きの雰囲気を、無理にこちらに注意を向けさせるような無粋はしない。その場の流れに従えばOK。) - シメだと張り切って自己顕示するよりも、場を和ませ、参加者全員が気持ちよくお開きできることが一番重要。
アキポリ編集部より
ビジネスシーンにおいて、プレゼンテーション力が重要なテーマであることは、誰しも認識していることと思います。 過去を振り返ると、誰でも一度は、プレゼンで大失敗の経験や忘れたくなるほど嫌な思い出が残っているはずです。 一方で、事前準備不足や本番での極度の緊張など、失敗の理由はわかっていても、あまり思い出したくないのも事実です。 また、緊張や失敗の理由を、自分以外の外的要因-例えば、マイクやPCなどの機器の不具合、部屋や会場などの環境、お客様や聴衆のレベル-のせいなどにしたくなる心理もわからなくはありません。 そのために、自分にとってプレゼンテーション力は重要なテーマであるはずなのに、振り振り返りやレビューのしづらい心理的理由が大きく影響し、自己成長が難しいテーマになってしまっています。
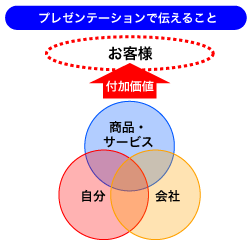
もうひとつ、プレゼンテーションが難しい理由として、単に、“言葉”や“意味”伝えるということではなく、お客様や聴衆に対して、こちらの“想い”や相手にとっての“価値”を伝えることがプレゼンテーションの目的であることがあげられます。 会社や自分、あるいは商品やサービスについて説明することを、プレゼンテーションとは言いません。自分の会社や自分とお付き合いいただくと、あるいはこの商品やサービスを利用していただくと、相手にとってどのような価値があるのかをイメージできる=メッセージが伝わることが「プレゼンテーション」なのです。
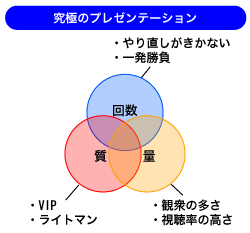
一概に「プレゼンテーション」と言っても、大きなプレゼンから小さなプレゼン、重要なプレゼンプレゼンからそれほどでもないプレゼン、一発勝負のプレゼンからやり直しがきくプレゼンとシチュエーションによって様々です。 シチュエーションの要素を、右図の回数×質×量の3つでとらえると、究極のシチュエーションは、やり直しがきかない一発勝負(回数)×重要な人に向けて発表する(質)×聴衆が多い(量)場合と言えます。
アキポリ編集部では、究極のプレゼンの達人といえば、本番一回のみとったシビアな状況で、重要な人も含めて、多くの聴衆・視聴者にメッセージを伝えることが求められるアナウンサーやキャスターではないかと考えました。 テレビなどの華やかな場は、通常多くのビジネスとは対極にあるように思われがちです。しかし、むしろ、生本番のみ、数字(視聴率)による評価、不特定も含めた多くの人へのメッセージ伝達、生業ゆえに厳しい自己レビューの繰り返しといった環境において、プロフェッショナルとして生き抜いてきた人に、ビジネスの場でも活用できる極意が隠されているのではないかと考えています。
また、プレゼンテーションでは、自己演出も重要です。自己演出とは、相手にメッセージを伝えるために必要な要素-言葉以外に立ち居振る舞い、表情、仕草など-をその場に合わせていかに効果的に自分を演出できるかということです。アドリブもその一つといってもいいかもしれません。 自己演出やアドリブといえば、やはりアナウンサーやキャスターの方にとって、多くの経験の中によって磨き抜かれた技を持っている得意分野と言えるでしょう。
そこで、今回は、女性スポーツキャスターの第一人者である出光ケイさんにご登場いただき、フォーマルな場に限らず、ビジネスにおける様々なシーンでのプレゼン・自己演出の極意やヒントをご紹介いただきます。
アキポリ推薦 プレゼンの達人 出光ケイ氏


TBSテレビに日本初の女性スポーツキャスターとして起用、その後もスポーツジャーナリスト、テレビリポーターとして多方面で活躍。
主なレギュラー番組実績
■TV 「JNNスポーツチャンネル」「ビッグモーニング」(TBS系) 「ルックルックこんにちは」「ザ・ワイド」(NNN系)「あなたの知らない日本」(ANB系)、「オープニングベル」(TX系)、 「サンデー11しが」(びわこ放送)、「ナイト・イン・ナイト」(ABC)「桂三枝のスポーツマガジン」(MBS)
■ラジオ 「我が人生に乾杯」(NHK第一)、「サタデー・グリニッシュエアー」(T-FM)、「ジョイフルモーニング」(ニッポン放送)、 「ラジオ面白夕刊」(ラジオ日本)
関連記事一覧
-
 プレゼンの達人
プレゼンの達人
プレゼンの達人Case5
お客様からの信頼度が
ワンランクアップする乾杯の挨拶お客様からの信頼度がワンランクアップする乾杯の挨拶 -
 プレゼンの達人
プレゼンの達人
プレゼンの達人Case4
立食形式のパーティーやセミナーでの
スマートな交流の広め方立食形式のパーティーやセミナーに一人で参加するとき -
 プレゼンの達人
プレゼンの達人
プレゼンの達人Case3
会食や飲み会の席で
急に〆の挨拶を振られてしまったとき会食や飲み会の席で急に〆の挨拶を振られてしまったとき -
 プレゼンの達人
プレゼンの達人
プレゼンの達人Case2
移動中や外出先でお客様にばったり出会ったとき移動中や外出先でお客様にばったり出会ったとき -
 プレゼンの達人
プレゼンの達人
プレゼンの達人Case1
プレゼンやミーティングの場で急に自己紹介をふられたときプレゼンやミーティングの場で急に自己紹介をふられたとき