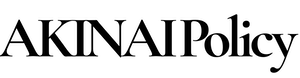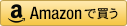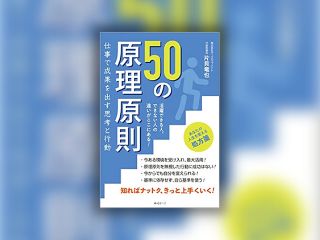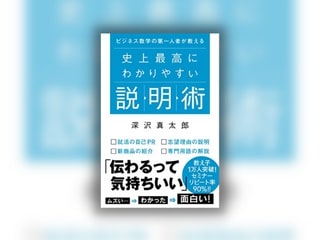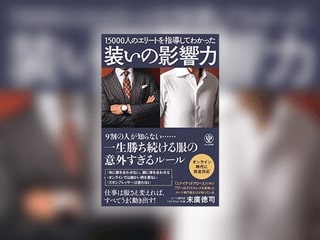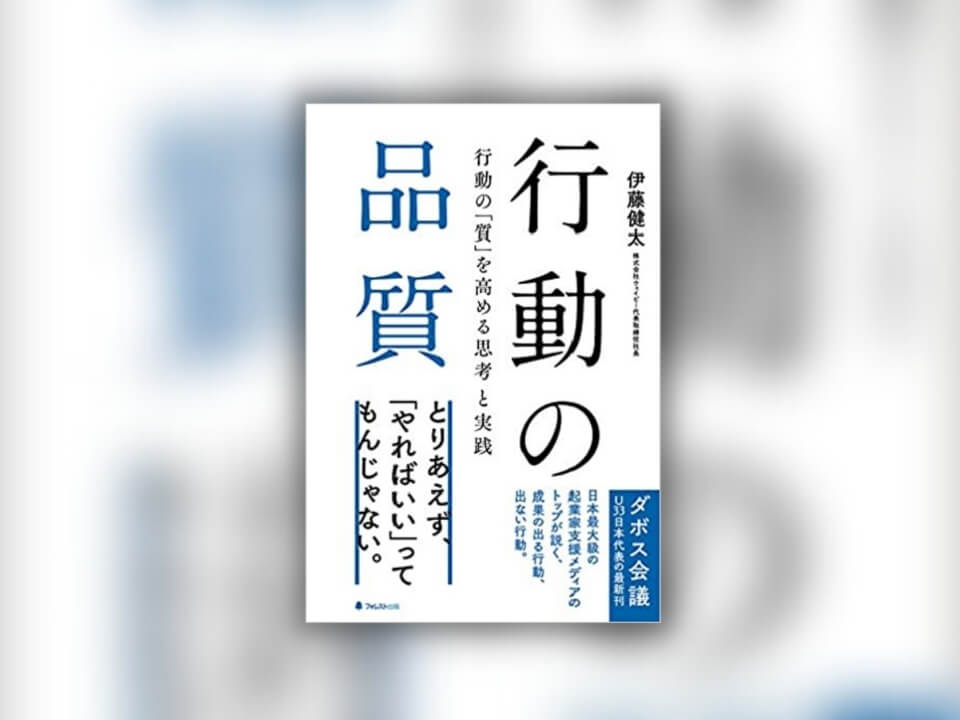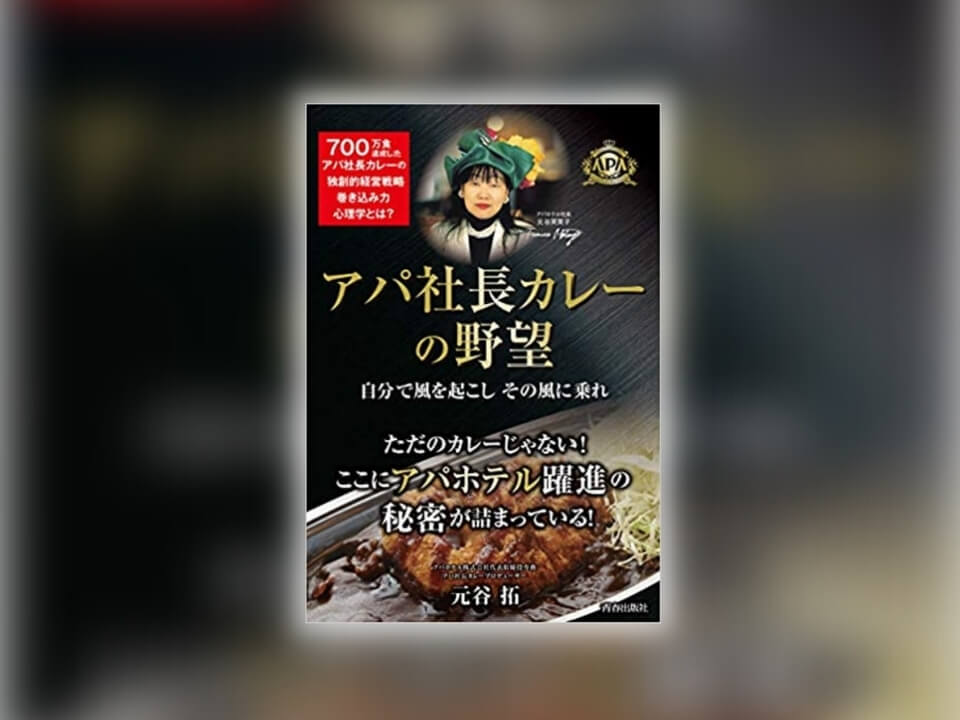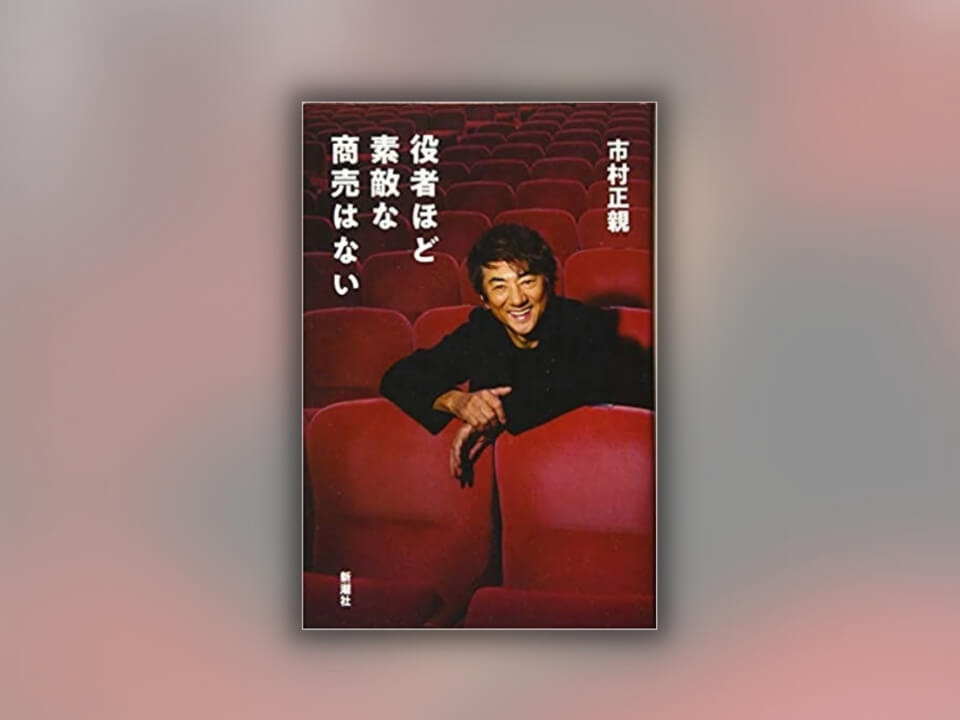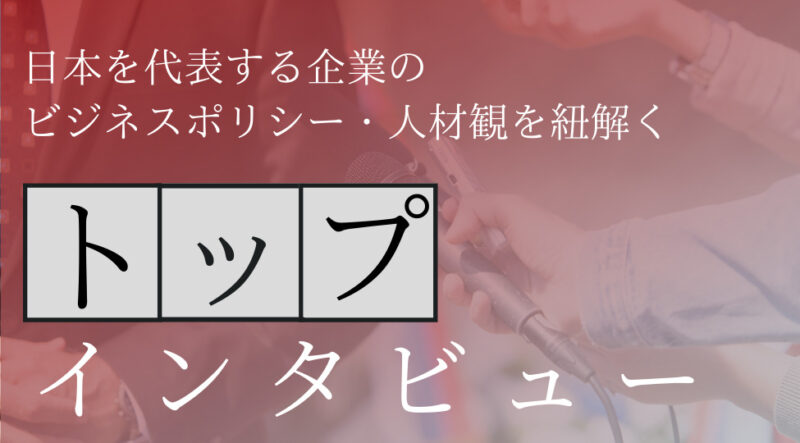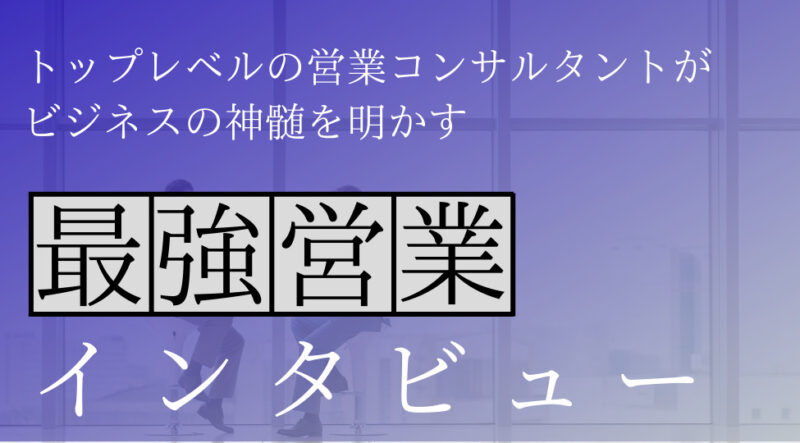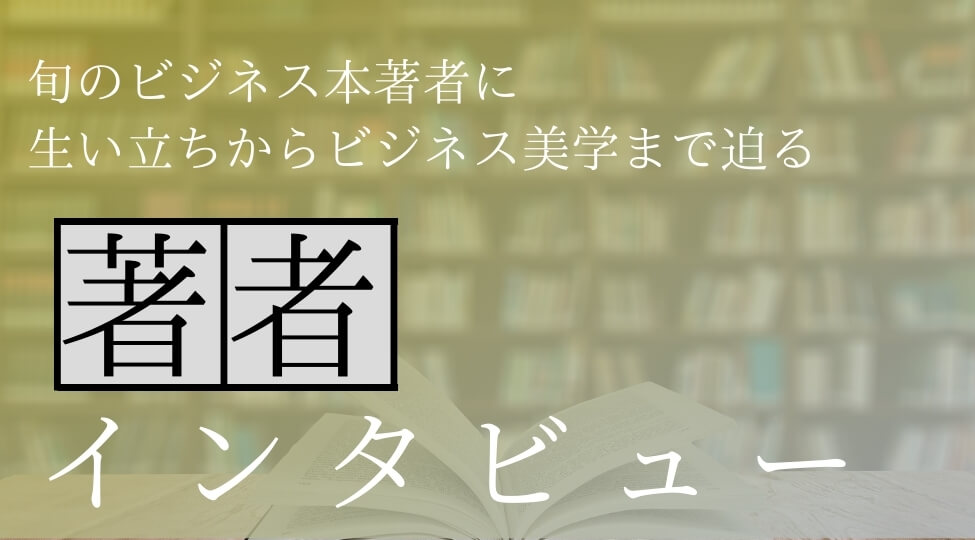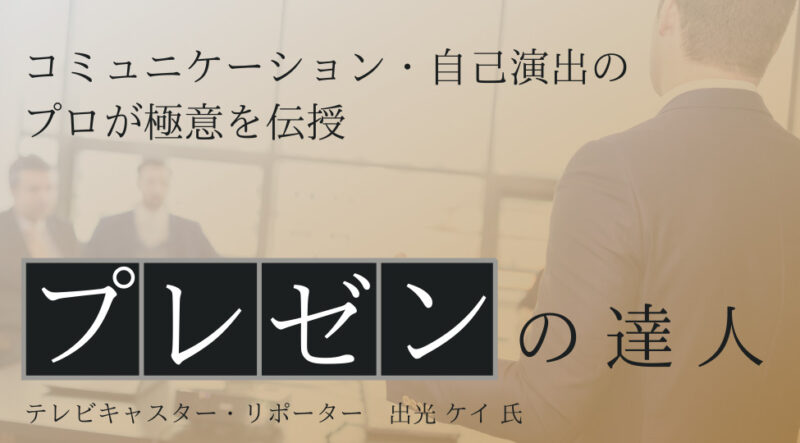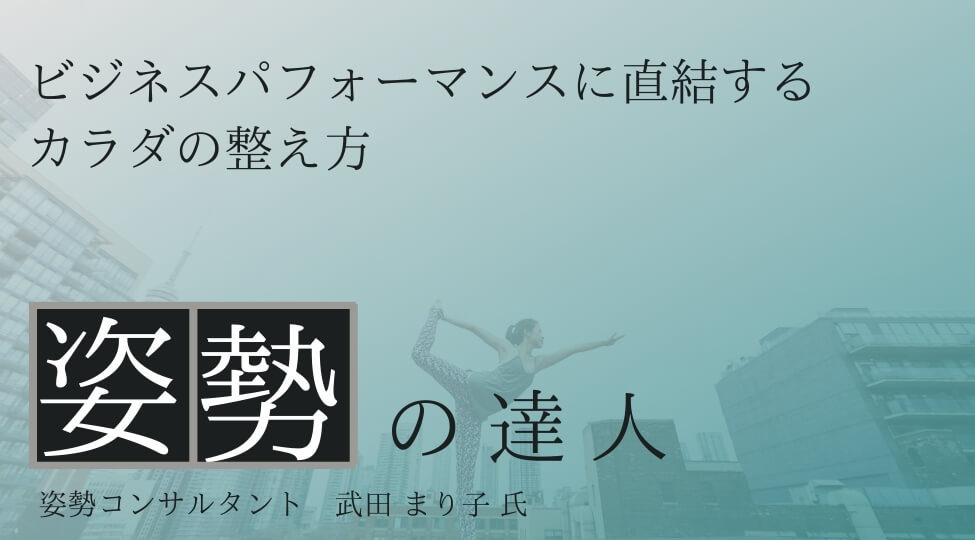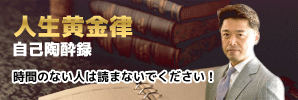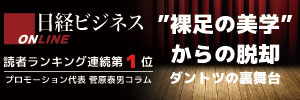株式会社ディ・フォース・インターナショナル
代表取締役
福島 章(ふくしま あきら)氏


著者プロフィール
元気を出す営業開発コンサルタント、人材開発トレーナー、株式会社ディ・フォース・インターナショナル代表取締役。
大学卒業後、通信機器メーカーに入社。入社以来、数々のプロジェクトをリーダーとして牽引。
ベンチャー企業2社での営業&マーケティング担当役員を歴任し、2000年に営業開発コンサルタントとして独立。
不安定な経営基盤のベンチャー企業時代に、自立型営業人材育成の重要性に気づいた経験から、さまざまなビジネスの立ち上げ営業指導を行なう傍ら、プロの人材開発トレーナーとして、広くビジネスパーソンの能力開発に従事している。
これまでの指導実績は延べ18,700 人を超える。
執筆の動機
ビジネスはテクニックの前にマインドセットが重要
営業もひとたび「スイッチ」が入れば、ポジティブスパイラルが回り出す。
ご覧の通り、この本のタイトルは「営業スイッチ!」です。ですから、営業パーソンをメインターゲットにした内容になっています。営業だけでなく、広くビジネスパーソンに向けた本にしたかったのですが、出版もビジネスである以上、ターゲットを明確にしようと、どんなビジネスも営業なしに成り立たないことを踏まえて「営業」にフォーカスした内容でまとめました。 2000年に独立してから、出版のお話はこれまでも度々いただいていました。 しかし、私は自分の思いや考えを文字に落とし込むよりも、ライブ感のあるしゃべりの方が得意なのです。そのため、これまで出版のお話をいただきながら、そのままになってしまっていました。

チーム「営業スイッチ!」へ
ところが2年前、フリーの編集者とのご縁があり、「一度、企画書を出してみたら」と言っていただきました。そこで、企画書を作ってみてもらうと「これでは全然駄目です。福島さん、本当に出版する気はありますか?」と一蹴されてしまいました。「本気です!」と伝えると、編集者の方も企画書を添削してくださり、私自身も俄然やる気・その気になってきました。
ブラッシュアップした企画書を編集者の方と一緒に出版社へ持ち込んだところ、すんなりと「これは行けますね!」というお話になりました。
そこからすぐに出版に至ったわけではありません。実はその後も、結構大変だったのです。今度は出版社の方との100本ノックが始まりました。
「福島さんの伝えたいことを500個リストアップしてください」と言われ、知恵を絞りながら何とか盛り込みたい内容を書き出してみました。最初はほとんど駄目出しばかりで、出版社の方とのやりとりの中で何度も何度もブラッシュアップしていくうちに「営業パーソンのやる気の“スイッチ”が押せるようになる」というフレーズが浮かび、そこからタイトルの「営業スイッチ!」が生まれました。 この本を手にとられた方には、自分の中に眠っている力を起こして欲しい、自分の中に眠っているスイッチを入れて欲しいと思います。 私は日頃から「気付けない人は、ずっと気付かない(成長出来ない)」と言っています。言い方を変えると、ひとたび気付けば、人はこれほど成長するのかというほど伸びていきます。 このわずかな違いがあなたを劇的に変えるきっかけとなり、自分の力を最大限に発揮する方法を実践することで、お客様にとって価値あるものを提供し、お客様から信用・信頼され、一目置かれる存在となっていくのです。 出版社の方との打ち合わせのなかで、ビジネス本は読者にとって実効的なテクニックを紹介しないと売れないという指摘を受けました。 しかし、「スイッチ」の本質はテクニック以前のマインドセットの問題です。テクニックに終始してしまうと、私が本当に伝えたいことが伝えられません。この本の編集過程では、この点で出版社の方と何度も議論を重ねました。 この本では「営業スイッチ」として、
- 「思考スイッチ」
- 「必達スイッチ」
- 「メンタフスイッチ」
- 「受信スイッチ」
- 「発信スイッチ」
- 「巻き込みスイッチ」
- 「成長スイッチ」
の7つについて解説しています。 最初のスイッチが入ると、次のスイッチに良い影響を与え、さらにその次のスイッチに、その次に・・・と順番にスイッチが入っていきます。そして、日常の行動・思考の中で、これらがポジティブスパイラルとして回っていくようになります。7つのスイッチが円を描いていくので、中心から見たら同じところをぐるぐるしているように見えますが、全部のスイッチが起動し一周して戻ってくると、以前の自分よりも次元が上がっているため、実はトルネード状に深みが増しているのです。この良いサイクルが実感できると、自分自身の持っている能力は飛躍的に開花していきます。 私の研修の受講中は同じところをぐるぐると足踏みしていた人が、この本を読んだことで研修の内容が腹に落ちたといってくれた人もいました。 この本をきっかけに皆さんの中にある「スイッチ」が入り、お客様から一目置かれ、同時に自分の成長を実感できる営業パーソンが一人でも多く増えていけば、嬉しく思います。
生い立ち
幼少期 ~兄と妹に挟まれた中間子が編み出した生存戦略とは?
父はサラリーマン(営業)でしたので、私の今に至るキャリアは父からの影響を少なからず受けていると思います。
私は3人兄妹の真ん中で、3歳上の兄と5歳下の妹がいます。
長男の兄は家族の中で、当然、父の次に大事にされます。もちろん、兄妹の中では一番上ですので、怒られるときにも矢面に立つのは長男ですが、逆を返せば一番人格が認められているということです。
妹は男2人の後の末っ子で女の子ですから、これはもう可愛がられる存在でした。
長子としてリスペクトされている兄と、家族のアイドルとして可愛がられる妹。中間子の私は、幼な心にも「このままでは自分の存在価値がなくなる!」との危機感を持ち、人とは変わったこと、変わった考えを好むようになりました。
この時、子供心で考えた生存戦略が、今の私の行動・思考特性のルーツになったと思います。
小学校時代 ~転校先のクラスでいきなりの存在感
父の転勤の関係で、小学校5年生のときに、横浜から埼玉の北部に引越しをしました。
今から思うと生意気ですが、横浜のお洒落シティ・ボーイを気取って、小学校の頃から長髪にしていたちょっと変わった子でした。
それが埼玉に引っ越すと、周囲は坊主頭の純朴な子供たちばかりです。転校日当日、なぜだか先生が私を紹介することなく教室にひとり残して出ていくと、好奇心を抑えきれない同級生たちがわあーっと集まってきました。そして、口々に「ねえねえ、どこから来たの?」「名前は何ていうの?」と質問を浴びせてきます。都会から田舎への転校で少し斜に構えていた私は「何だよ、人に名前を聞くなら先に名乗れよ・・・」と心の中で思っていました。そこで口に出た言葉が、「『名前は?』って聞くなら、当ててみろよ」というせりふでした(笑)。
これが先制パンチとなって、転校から3日も経つと、クラスの中心的存在になっていたように思います。このときの同級生には今でも交流のある友だちがたくさんいますね。
中学校・高校時代 ~初めて自分の「スイッチ」を開発した経験

中学校は、同じ小学校からの持ち上がりも含めて1学年350人くらいでした。
小学校のときからあまり勉強はしなかったので、初めてのテストは学年で150番台くらいでした。
ところが負けず嫌いの性格が顔を出し、「勉強法を開発すれば、できるようになるんだ!」と豪語していました。実際に自分なりの効率的、効果的な勉強方法を編み出し、実践してみたところ、成績は学年で30番→10番と上がっていきました。
高校時代 ~サッカー一辺倒の生活から浪人覚悟で受験勉強

小学生のときからサッカーをやっていたので、高校は文武両道の高校に進学しました。
通学は学校まで12キロの道のりとなり、毎日毎日ひたすら自転車で通いました。
そのうち自転車のチェーンがしょっちゅう外れるようになったので自転車屋さんに見てもらったところ、チェーンとかみ合うクランクがひどく磨耗していて、「ここまですり減ったのは見たことがない」と言われてしまいました。それもそのはず、1年間に1万キロ近くを走っているわけです。この自転車通学が、足腰とメンタルを鍛えてくれたのでしょう。 家の方針では、大学進学にあたって浪人はさせないということになっていました。

ところが、高校ではあまり勉強せずスポーツに没頭してに来てしまっていましたから、一度は本気で勉強しようと決意し、親には浪人させてもらえるようお願いして、許しを得ました。
それまでは理系選択だったので数IIIまで履修し推薦で行ける大学もあったのですが、文系への転向と、どうせ浪人して進学するなら六大学に行きたいと考えていました。
残念ながら第一志望の早稲田大学はマークシートを失敗し合格はかないませんでしたが、明治大学に進むことになりました。
大学時代 ~企画会社のアルバイトでビジネスマインドが萌芽

大学に入るとお金を稼ぎたいという思いが強くなり、授業やサークル活動には目もくれずにバイトに精を出していました。
直接的には、彼女とのデート代や当時は若者のステータスだった自分の車が欲しかったのが理由です。(当時人気の「86レビン」(懐かしいですね)という名車を狙っていたのです)
王道のアルバイトでは、学習塾の講師、家庭教師をやりました。現在の研修講師につながる「教育」には、この頃目覚めたのかもしれません。「育てる」に関係するといえば、同じ頃、親戚に生まれた双子が本当に可愛くて、将来は保育士になろうと思ったこともあります。 手っ取り早く稼ぐ時給効率の良いアルバイトでは、工場のラインや飲食業の深夜シフトなどもやりました。飲食のアルバイトでは、店全体を見る必要からオペレーションの課題などに気付く良い経験になったと思います。 そのうち、報酬だけではなくもう少しビジネスに直結する仕事がしたい考えて、大学3年生の時に恵比寿の企画会社でバイトを始めました。
この会社では、あらかじめ決められた役割や仕事だけではなく、企画書を書いたり、マーケティングのために取材や調査に行ったり、社長の原稿をタイプアップしたりとかなり幅広く、また頭も使う経験をさせてもらいました。
その中で、接点があった広告代理店に興味を持つようになりました。
もともと仕事をするならビジネスの最初から最後までに関われる仕事をしたいと思っていたので、大手の広告代理店ならそれができると考えたのです。 第一志望は電通に決め、ツテを頼ってOB訪問したり、営業の責任者の方にお願いして人事の模擬面接をセッティングしていただいたりしました。当時も広告代理店は人気企業で、1人当たり持ち時間5分で1万人を面接していたと言われていた時代です。本番と同様に5分でやってもらった模擬面接のフィードバックは散々なものでした。曰く、「君はどこから来て、どこに行こうとしているかのベクトルがまったく見えない」。確かに指摘の通りでした。そこで、自分自身と向き合い、自分の軸(強み)は良い意味で「攻撃的なところ」と決め、面接に望みました。残念ながら内定には至りませんでしたが、1万人の中から300人までには残りました。
そんなとき、中学の同級生で高校から学校が違ってもずっと友だちの一人が、「この会社は僕じゃなくて、福島くん向きだね」と言って、自分の就職活動で調べた時のユニデンのパンフレットをくれました。
そのとき、最初から最後まで関われる仕事は、代理店ではなくクライアント側になるのもありだなと思いました。ユニデンは自社ブランドを前面に出した製品よりもOEMを得意とし、また海外展開も積極的に行っているユニークなところも自分に向いていると感じたのです。
就職・ヘッドハンティング・独立
~新事業の立ち上げ経験と経営視点を学ぶ

新卒入社の同期は60名ほどいました。
ものづくりに携わるなら、マイナーな自社ブランドよりも大手メーカーのOEMと考え、1年目からOEM営業担当となりました。
OEMは製品ありきのプロダクトアウト型の営業とは異なり、顧客に対してまさに提案営業を行うスタイルです。大学時代のアルバイトで鍛えられた企画書の作成経験がここですぐに活きました。当時は家電メーカーのみならず、ときには化学会社までもが自社ブランドでコードレス電話を作りたがっていた時代で、マーケットそのものも拡大していました。市場環境が良かったことと大学時代のアルバイト経験が活かせたことで、仕事をすればするほど自分の業績は上がっていきました。
一方で、オーナーの意向による上司の降格や退職も目の当たりにし、資本主義のシビアな本質の一面を見る経験もしました。 2年目になるとソニーを担当し、香港を中心に海外出張に飛び回る毎日でした。新卒社員ながら1年目で成果を出し、だいぶ自信もついてきたのだと思います。2年目になると、スーツをすべて新調し、眼鏡も金縁に変え、シャツの上にはサスペンダーまでするスタイルで、若気の至りとは言え今振り返ると随分“イキッた”格好をしていたと思います。外面・内実ともに自信と実績をつけ、3年目には最年少で係長に昇格しました。

その後は、北京駐在を命じられ、新しい合併会社の立ち上げに奔走しました。しかし、中国で誤った情報をつかまされて20億の余剰在庫を抱え、発覚から2週間で本社に強制送還となりました。戻ってからは、古巣のOEM部隊で営業活動の傍ら、業務標準化・マニュアル整備など業務改善を中心に、着実な事業品質の向上を推進していました。その後、国内事業の再立ち上げにおける経営との戦略の相違がきっかけになり、ヘッドハンティングを受けて社員120名ほどの大阪のベンチャー企業に移籍することにしました。 ここはパッケージソフトのアウトソーシングをしている会社でしたが、コンテンツを伝送でデリバリーする新しい事業の責任者として着任しました。

(本人:お店の子供をだっこ)
それまでは、上場会社の看板と組織、体制、制度などに守られていましたが、ベンチャーでは雇用形態、評価制度、給与など、社員には自立と成果を求める厳しい環境に変わりました。しかし、これも自分で選んだ道です。
前職でも大手企業との交渉や海外駐在など、ある程度の権限と裁量は持たされていましたが、あくまでも会社の事業の一部を遂行するためのもので、先方のカウンターパートも事業実務レベルの人たちがほとんどでした。
一方、移籍したベンチャーでは、様々なタイプの経営者に会う機会が増えました。また、社長の名代として会合などに出席することもあり、事業レベルにとどまらず、企業まるごと・経営まるごとの視点を持つ人たちとに触れる機会と人脈形成ができたことは大きな財産になりました。
この会社では、任されていた新事業の開発方針について社長と考えを異にすることになり最終的に退職しましたが、自分自身のキャリアにとっては、前職からリスクをとって移籍しただけの大きなメリットがありました。
このあと、外資系ファンドが出資するベンチャーに移籍したのち、ちょうど2000年を迎えた年に独立することにしました。
ビジネス美学
営業に元気なくして、企業に元気なし
営業が必要ないビジネスはありません。営業がビジネスをつくり、企業をつくる源泉であるといっても良いと思います。
ですから、営業に元気がなければ、その企業には成長は望めません。
私が独立したきっかけの一つは、最後に勤めていたベンチャー企業の経営メンバーだった投資会社の人の言葉です。営業は企業・ビジネスの第一線として、マーケット・顧客に直接触れています。営業の声は、企業の成長と発展のためにしっかり経営にフィードバックされるべきものです。今の事業のままではではお客様が喜んでいないということを、その時の経営メンバーは理解していませんでした。理解していないというより、敬意を持って営業の声に耳を傾ける姿勢を持っていなかったのです。
反骨精神 「負けない!」という気持ち
このベンチャーでの出来事が、「よし!今に見ていろ。営業なくして、ビジネス・企業は成り立たないということを証明してやる!」という強い思いを引き出し、独立のエネルギーとなりました。
思えば、企業に勤めていたときからこれまでも、負けたくない!という反骨精神は、変わらず私の美学であり、ビジネス推進の原動力になっているように思います。
将来の夢
「営業スイッチ!」がインストールされたビジネスパーソンを
輩出し続けていきたい!
人の抱く価値観とは、時代や環境の影響を大きく受けて形成されるものです。その価値観は、様々な人との出会いや様々な経験、思索の繰り返しで、磨かれたり、進化していきます。「営業スイッチ!」をインストールすることができれば、ビジネスパーソンは、一本筋の通った揺るがない軸(価値観)を確立していくことができると思います。
私も、振り返れば、「カッコよさ」という価値観を大事にしてきたのだと思います。学生時代や20代の若い頃は、たくさんのお金を稼ぐことをカッコいいと思っていました。30代でベンチャー企業に転職し、様々な経営者との接点を持つようになると、優雅な白鳥が水面下でものすごい勢いで水掻き、どんな泥水を飲んでも人前では笑顔でいるようなオーナー経営者の美学やタフさにカッコよさを感じていました。40代になると自分自身にも厚みがでてきたお陰だと思いますが、「表面的で浅い人」「見かけだけの薄っぺらい考え」が自然と見えてしまうようになってきました。今では「ずっとぶれずにやり続けていくこと」「揺るがぬ自分の軸を持った上での臨機応変さ」をカッコいいと感じるようになりました。
これからも、この「カッコ良さ」を1つの軸に、人の元気、ビジネスの元気、会社の元気を創る!営業開発コンサルタントとして、営業力・影響力を発揮し、ビジネスパーソンの「軸づくり」に貢献していきたいと思います。一人でも多くの営業パーソンがお客様の信頼を獲得し、元気で“顔晴れる”(がんばれる)よう、そして、一社でも多くの企業が元気になれるよう、「営業スイッチ!」を押し続けていきます。
■取材チームからの一言

元気な人の発するエネルギーは、周囲の人に良い影響を与えます。
「オーラ」とか「気」とか、科学的には存在の証明が難しいものでも、こういうものが周囲へ影響を与えているという現象=事実をベースにすると、そこにはやはり無視できない力が存在していると思います。
福島社長は、とても元気で“ご機嫌”な空気をまとった人です。この人の研修を受けたら、きっとエネルギーがチャージされるのではと期待させてくれる雰囲気を持っています。
マーケットそのものが拡大していた日本の安定成長期・バブル期に、若い時の持てる力を余さず発揮することで、組織の中できちんと成功体験を積まれたことが、基本的に健全な精神とポジティブな思考のベースになっていらっしゃるのでしょう。その後のベンチャーでは新規事業責任者というキャリアを積むとともに、経営との事業方針の対立など、必ずしも順風満帆とは言えない経験や、独立後のご苦労など、ネガティブなことにも正面から向き合い、乗り越えてこられました。これが現在のお人となり、ひいては研修に深みをもたらしているのではないでしょうか。

少し前に「KY」という言葉が流行りました。この本のなかでも「KY(空気が読める/読めない)」営業から「KT(空気をつくる)」営業へという一節があります。
だだ、空気が読めるにしても読めないにしても「KY」にとどまっているうちは、あくまでも受動の立場です。ここから、一歩前に出て空気をつくり出していくのが「KT」であり、受動から一転、能動に変わるのです。
営業にかぎらず、自分の内なるスイッチを押せるのは自分だけ。この本は、その人の内なるスイッチが起動するよう「気」付きを促す行動や考え方が示されています。
これからも福島社長は自らのスイッチを起動し続け、さらに一人でも多くの営業パーソンが自分のスイッチに気付くことで受動から能動に“スイッチ”し、お客様も本人もハッピーになれるようポジティブなエネルギーを放射し続けていかれることと思います。
My Favorites
オススメの本
よく行くお店
よく行くお店
出先でのローカルなB級店
ビジネスで使えるお店
帝国ホテル メインバー 他
ペニンシュラ
リッツカールトン
マンダリン オリエンタル東京 などホテルラウンジ及びバー